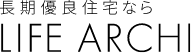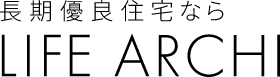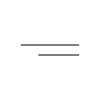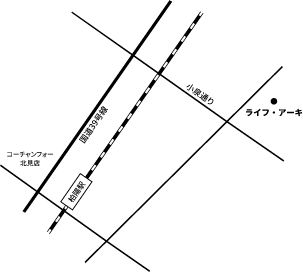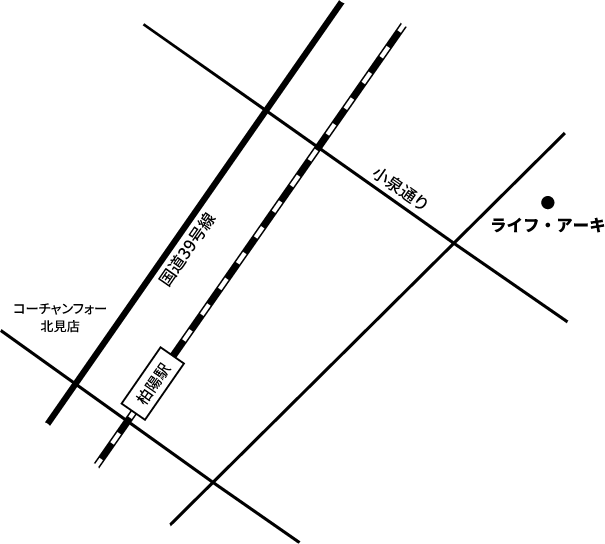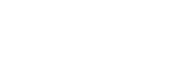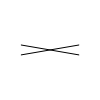よくあるご質問
Q&A

資金・予算に関すること
住宅ローンの返済計画はどう考えるのが良いですか
年齢と職業、年収から、最初に銀行が貸してくれるであろう金額を先にお知らせします(予想よりも借りなくても良い事が多いです)。現実的に払える額をベースにお打ち合わせをしていきます。調達方法によって金利や条件が変わるので、どこの銀行で調達すべきかなどや、返済シミュレーションを考えていきます。金額や調達に困っても、家を諦めるではなく、長期的に実現する方法を一緒に模索します。
変動金利と固定金利の選択で迷っています
私たちは固定の10年からシミュレーションすることをベースに考えていきます。道内の主要な銀行では、変動金利でもメガバンクよりは低く無い傾向があるので、フラット35か、固定10年で考えていきます。変動金利のリスクや、固定期間のあるものもリスクを鑑みてアドバイスしていきますが、まずはいくら払えるか、というベースを崩さないように考えていきましょう。
自己資金と借入金のバランスを決められません
手元の自己資金があり、選択肢を持っている人には、自己資金は全部入れずに手元のキャッシュを残して借り入れることを推奨しています。できるだけ今の選択肢を増やし、自由度を高められることがリスク回避にもつながります。ローン期間も、長く組んで余裕資金があれば繰り上げ返済をするように。自由に選択肢を広げられるように。払うべき額よりも多くキャッシュを持ち、生活に備える事や早期返済に備える事を重視すべきと考えています。
建築費以外の諸費用(登記費用、税金、保険)って、どれ位かかるんでしょうか
必ず、見積もりを作る際に、建築費以外のコストを見積もりで出すようにしています。家具や引っ越し代などは計上しませんが、銀行への手数料や登記費用(手数料、印紙、税金)、火災保険、外構、土地の金額、仲介手数料、固定資産税、名義変更の登記費用など、諸々の諸経費についてもしっかりと積算していきます。
家を建てる時に使える補助金や助成金はありますか
基本的に使えるものは使う方針でお話ししますが、新築とリノベ、リフォームでも使えるものが違うので、工事内容で一番経済性の高い方法の選択肢をお示しし、ご活用いただきます。手続きなどもサポートし、最終的には相殺した金額で精算いたします。
建築後の固定資産税ってどれくらい注意が必要ですか
新築に対しては金額的にそこまで大きく変化しないため、気にしないで進めましょう。リノベーションは申請が必要で、固定資産税の評価が大きく変わる可能性があります。固定資産税が上がってしまうことに対するリスクだけでなく、それに該当する補助金メリットなどを鑑みて、総合的に考えられるようサポートします。
水道やガスの引き込み費用の検討がつきません
土地を見に行った時点で概ねの費用感がわかります。都市部から離れるとの土地の値段は下がる傾向がありますが、引き込み費用などが高くなってしまうことにも注意が必要です。水道管が近くにあっても土地が広い場合など、引き込み費用も鑑みて設計する必要があります。できるだけ早い段階で明らかにしていきましょう。
将来の修繕費や維持費はどう考えれば良いでしょうか
根本的には、寿命が長くなる施工方法や部材を選定することをお勧めしています。長期優良住宅には定期点検があり、国への報告義務がありますが、大きな修繕が必要になる前に早期発見し、簡単に治せるうちに直しておく。体の治療と同じ。コストはかかるが、小さいうちに治すことが大事です。
予算内でデザインと機能のバランスの見切りはどう付ければいいですか
新築に関しては、長期優良住宅の要件を満たすことを推奨しています。理想的な機能を費用の問題で達成できない場合は、リノベーションも推奨します。
見積書の詳細確認で気を付けることはなんですか
地盤調査は見積もりに入れられない要素なので、注意が必要です。また、やむを得ない追加要素もあります。お客様との相談で設計を変更する場合に予算が変動することはありますが、基本的には見積もり段階で全て盛り込むようにしています。お客様にとって借り入れの事情など値段は変えようがないので、不確定要素も含めて説明し、費用として計上しておきます。漏れなく詳細な見積もりを出すことが重要です。(契約後の追加は原則しない。全てを詳しく記載する方針。)
土地選びに関すること
土地の将来の価格などは予想できるでしょうか
将来的な流動を鑑みて著しく価格が下がらないよう、居住誘導地域を意識して土地選択をしてもらうことをおすすめしています。
土地の形状や広さの良し悪しがわかりません
実現したい暮らしのビジョンを実際に実現できそうかをイメージしてもらえると良いです。世帯構成に応じた駐車場の配置も考えてみてください。
地盤の強さや安全性についてはどの程度考えるべきでしょうか
実際は調査しないとわからないことが多いですが、これまでの経験から概ねのアドバイスができる可能性があります。
道路との接しかたや特殊な土地の注意点は?
道路から離れている立地や高低差がある立地は、対応費用がかかるケースがあります。メリット・デメリットを総合的に考えましょう。
周辺環境(交通、学校、病院)を考える時のポイントは?
学校だけでなく、居住誘導区域、バス路線などの公共交通の利便性、スーパーなども含め、長期的な生活環境の利便性を評価項目とするべきと考えています。
日当たりや風通しはどのように考えるのが良いですか
日当たりが悪そうな土地でも、住まい方や設計でどのように補完できるかを考えていくのが大事です。
騒音や匂いなどの住環境リスクを把握する時の注意点は?
事前に立地の特性を意識してもらえるようアドバイスをします。近所がどんな環境なのか、事前に理解することが大事です。
法的な建築制限(建ぺい率、容積率)にはどの程度注意が必要でしょうか
新築ではあまり気にしなくて良いのですが、中古物件が違法建築になっていないかどうかは要注意です。
土壌汚染や地下水のリスクはあるのでしょうか
北海道においてはあまり気にしなくても良いと思います。地下水に関しては事前にリスクを説明します。
地域特有の気候特性(雪、湿気、強風)を知るには?
雪が多いエリアは除雪しやすい家にするなど、留意事項を踏まえた設計をします。最近は異常気象が多いので、ハザードマップについては留意しましょう。
設計に関すること
家族構成と将来のライフステージに対してどう考えるのが基本?
車椅子や老後のことなど、どうなるかわからない可能性よりも、今イメージできることに着目を。将来どうなるかわからないことにコストを出したり、バランスを欠いたりするよりも、長期的な資産価値や選択肢を考えることを重視しています。
部屋数や間取り、なかなか判断がつきません
まずは、家族と暮らしたいライフスタイルを考えてみていただき、予算という前提の中で、家族構成、住み方、仕事、趣味など、総合的に考えていきましょう。水道の引き込みや立地なども含めて考えるものなので、プロの力を借りましょう。
プライバシーの確保はどの程度必要でしょうか
寝室、オープンスペースなどに対して、自分のプライバシーに対する考え方を整理することが必要です。それを踏まえて、中だけでなく、外からの外観なども考えていきます。
収納スペースの配置と容量。一般的にはどの程度でしょうか
収納スペースは分散させて設置するのがセオリーです。大きいスペースにまとめて、というよりも、各所に分散させた方が使う時に楽になることが多いです。予算があれば家族の荷物をまとめた収納も使いやすい考え方です。容量については現状のものが収まれば十分、捨てられない人、捨てられる人、などの傾向もありますので、増えていくのはあまり考えないで、今あるものをベースに考えるのが良いです。
動線(家事動線、生活動線)の決め方がわかりません
生活スタイルを想像して、書き出していき、それに合わせて動線を考えるのがセオリーです。例えば、洗濯を朝する人、夜する人、家事の負担割合や家族構成、10年後を目安に、今しかいらないもの、今後も必要なものを判断して考えていきます。
天井の高さや窓の位置を決める留意点はなんですか
採光性、プライバシーの確保、開放感と閉鎖感の好みの観点で、バランスをとり設計しますが、構造にも関わってくるところがあります。
自然採光の影響はどういったものがありますか
自然採光では、直射日光で、床や壁、インテリアに対する日焼けの他、温熱の影響として、暑い、寒い、などへの影響もあります。外からの視認性にも関わるところなので、プライバシーにも考慮しないといけません。採光を重視しても、、結局カーテンを閉めっぱなし、ということもよくあります。
キッチンや浴室の使いやすさのポイントは?
大きさだけでなく、素材なども重要で、キッチンはステンレスの方が汚れがつきにくいと思います。収納の量も大切です。人造大理石などは色移りすることもあります。風呂については、掃除のしやすさを考えておくのが重要です。
ワークスペースを置くときのコツはありますか
何をするかにもよりますが、基本は閉鎖性の観点で考えていきます。ワークスペースだと、書類の仮置きや、会議などの見た目も意識して、意外と収納スペースが重要だったりもします。トイレなどが近いところにあると便利に使えます。
廊下や階段の幅や安全性について
使い勝手としては一般的なサイズで十分不便はないので、廊下よりも普段使うスペースに面積を割いた方が良いと考えています。
リビングとダイニングの一体感に関して注意事項はありますか
一体感があればあるほど、開放感は高まりますが、食事の状況などが影響するので、プライバシーや住み方の好みなどで決めるのが良いです。
洗濯物を干すスペースの確保はどうしたらいいですか
極力確保できた方が良いのはもちろんですが、スペースを使うので、電動の物干し竿などを洗濯機の上に設置して、高さで確保するという考え方もあります。
トイレや浴室のプライバシー設計は重要性について
あった方が良いものではありますが、トータルの面積を圧迫してしまうものでもあります。
屋根裏や床下を活用するのにデメリットはありますか
屋根裏については、断熱層の確保が難しくなることもあります。高断熱とは相反する考え方なので、断熱性能を上げるのにコストが上がってしまうこともあります。床下はデメリットはあまりないので、合理的ではあると思います。利用頻度の低いものを置くのには良いと思います。
ゲスト用の部屋やトイレを設置する際の留意点はありますか
最初は要望されることも多いものでもありますが、必ずしも必要なものでもないと思います。子供が成長した後のことも考えると、部屋は後々余る傾向もあります。今と、将来のバランスも考えましょう。トイレは、水回りのお掃除のことも考えると良いです。将来のことを考えてリセールし易い家にしていることも大事です。
オープンスペースと仕切りの柔軟性についてどう考えたらいいですか
仕切りは柔軟に間取りやプライバシーのコントロールができるので、導入、活用するのは良い考えだと思います。
自然素材の使用(木材や石材)についてどう考えたらいいですか
質感などが出る良さもありますが、手入れなどは一般的な構造物よりも手がかかることもあるかもしれません。木材は汚れやシミ、カビなどにも注意が必要です。
家全体の統一感(デザインと機能)についてどう考えたらいいですか
自分の好きな色味や雰囲気をまずは見定めてから考えていくと良いと思います。それに合わせて性能や間取りを考えていきましょう。
ユーティリティスペースの確保(洗濯機や掃除用具置き場)は大切ですか
暮らしは便利になるので、優先度は高いと思います。最近だと、家事室、洗濯して乾かして収納するという流れを一体的に考えたスペースを作るケースがあります。
暖炉や薪ストーブの導入はどう思いますか
さまざまなデメリットを上回るメリットを感じる方にはおすすめですが、よく考えてご判断ください。
音響設計(ホームシアターや楽器演奏用防音部屋)について教えてください
専用の部屋までいかずとも、音響に配慮した機能を、普段使う部屋に持たせるようなこともありますので、音楽や映画が好きな方にはぜひ検討ください。
屋外のデッキやテラスを設置する時の注意点は?
家を建てた後に、どのように使いたいか、道路面との関係はどうか、など、当初から意識して設計が必要なので、できれば初めから考慮しておきたい要素です。
窓からの眺めをできるだけよくするにはどうしたらいいですか
まずは、その土地の景色の切り取り方を重視しましょう。次に、住宅街などでは、高い目線を大事にした眺望などを考えて窓を設置するなど、眺めをよくするテクニックがあります。外構でもカバーすることもできます。
建材や施工に関すること
耐震性について教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【性能と経済性】
断熱材について教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【性能と経済性】
省エネ設備について教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【性能と経済性】
使用する建材の品質と寿命について教えてください
建材の品質や寿命は、一般的な建材であれば大きな違いは少なくなってきているので、どちらかというとメンテナンスのしやすい形状や設計方針を持つことが大事だと思います。メンテナンス性によって、維持コストは変わります。隣地に近すぎると足場をつくるのが大変で、コストが上がるなどの要因もあります。もちろん、できる限り高品質でコストメリットの大きいものを提案します。材料とプランの両方を大事にしましょう。
害虫や湿気対策(防蟻処理など)について教えてください
シロアリは今は被害は多くないですが、長寿命を意識するのであれば、シロアリ対策は考えた方が良いです。北海道にも被害は発生し始めています。一般的な侵入経路などから対策することが可能です。
屋根や外壁材のメンテナンス性つにいて教えてください
建材の品質や寿命は、一般的な建材であれば大きな違いは少なくなってきているので、どちらかというとメンテナンスのしやすい形状や設計方針を持つことが大事だと思います。メンテナンス性によって、維持コストは変わります。隣地に近すぎると足場をつくるのが大変で、コストが上がるなどの要因もあります。もちろん、できる限り高品質でコストメリットの大きいものを提案します。材料とプランの両方を大事にしましょう。
職人の技術力や経験によって仕上がりが変わりますか
もちろん、職人さんによって仕上げの技術に違いはあります。だからこそ、メーカーの品質管理や考え方、信頼を重視したり、モデルハウスなどを見学して、職人さんが流動的なのか、固定されているのか、特徴を理解する目線を持つことが大事です。
防音性能を高める要素(窓や壁材)について教えてください
窓ガラスの厚さや、壁材、内部の断熱材選択、(繊維性のものの方が吸収性が良い)、2階の床に遮音シートなどを使うなど、見落としがちなところもあります。
環境に優しい建材を選択した方がいいのでしょうか
現在では、大体の建材が環境負荷に配慮されたものになってきています。特に制度上優遇されるものなどはありません。
配管や電気工事の品質による影響や品質確認の方法を教えてください
作ってしまうと見えなくなるところですので、設備業者さんと建築屋さんとの信頼関係や工程管理をしっかりと重視しているところで建てるのがベストです。
屋根を考える際の注意点を教えてください
雪国なので、雨落ち、雪落ちによって劣化・破損するリスクなどに配慮することは重要です。傾斜によるメンテナンスコスト、屋根の上にある雪の荷重については考えておいた方がいいかもしれません。今の技術では、屋根が平らでも雨漏りの心配はしなくても大丈夫だと思います。
排水設備の耐久性について教えてください
配管の寿命はかなり長いですが、熱湯などを流すと劣化してしまうことがあるので、使い方に注意しましょう。食洗機など、高温になる部分については、耐熱性のある配管を使うなどに注意です。それよりも、配管内の油や残留物への影響を考慮する方が重要です。
塗装の耐候性について教えてください
塗装は、塗膜が剥がれるようになってきたら替え時です。塗料や仕上げにもよりますが、一般的には10年くらいのスパンで考えるものです。金属の壁においても錆対策となるため、同様に塗膜は重要です。一般的なセメントのものは当然ながら塗料で保護しないといけません。
技術や設備に関すること
太陽光発電や蓄電池の設置について教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【性能と経済性】
高効率な冷暖房設備を選びたいです
エネルギー源として何を使うかは、まず考えるべき要素の一つです。例えば、灯油ストーブがあっても、夏は暑いからエアコンを使う、それならズバ暖を使う、など、選択肢はたくさんあります。まずはどのエネルギー源なのか、高効率のもので一つにまとめるかなど、複合的な要素を考えながら、最適な解を見つける必要があります。
給湯設備のエネルギー効率はどう考えるのがベストですか
国が政策的に効率の高いものを推奨している傾向があるため、補助が得られるようであれば、効率の良いものを導入することは経済的にも合理的です。
照明器具やコンセントの配置計画のセオリーと留意点を教えてください
普段過ごす場所や電気製品を使う場所に設置するのが基本ですが、子供部屋などはできるだけ明るく、リビングなどは居心地の良い光量を踏まえて考えるのが基本です。また、何も置かない場所にコンセントを設置することも実は重要です。家電に合わせて高さを設計します。
浄水設備は導入した方がいいですか
蛇口につけるケースが増えていますが、リノベーションでも水道配管は取り替えることが多いため、昔のように赤錆などが混ざるケースはほとんどありません。そもそも配管が汚れないような設計になっています。
オール電化の方がいいんでしょうか
昔ながらのオール電化はコストが高い傾向にありましたが、最新のオール電化はコストが下がってきており、重要な選択肢の一つとなっています。
IHクッキングヒーターやエコキュートってどうですか
掃除や料理のしやすさなどの理由からIHを選ばれる方が多いです。エコキュートも多機能なものが増え、太陽光と連動させて電気代のかからない稼働を自動的に判別するなど、技術が進化しています。
無線LANやネットワーク配線の考え方を教えてください
今は中継機などで対応できるため、Wi-Fiの電波などはあまり気にする必要はありません。むしろ、メンテナンスの際に作業しやすい場所に機械を置くことの方が大事です。
空気清浄や換気システムの導入について教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【家族の健康を守る】
維持管理やアフターサポート
アフターメンテナンスの一般的な保証内容や注意点は?
私たちの場合は、保証内容と保証書を明示してお渡ししています。当初は、まずはその保証書があるかどうかを確認することが大事です。一般的な法律もあるので、相談しやすく、保証外に対しても相談に乗ってくれるようなメーカーを選ぶのが大事だと思います。
設備や建材のメンテナンス性はどう考えたらいいですか
メンテナンスする側のアクセスのしやすさが考慮されていると、その後のコストが下がると思います
定期点検は必要ですか。頻度やコストは?
定期点検は、第三者の目で確認してもらえるので、お勧めしています。5-10年単位で、点検だけであれば数万円程度でできるかと思います。致命傷になる前に課題を早期に発見できると、年次ごとのメンテナンス計画なども立てやすくなります。
長期優良住宅に認証されるメリットを教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【性能と経済性】
壊れやすい設備はどんなものがありますか、交換頻度はどれ位ですか
常時稼働している設備が壊れるケースが多いです。換気システムなどは24時間動くので故障しやすかったりします。一般的には、ボイラーなども10年以上持つものが多いです。
法律や手続きに関すること
建築確認申請の手続きってどういうものですか、ハードルは高いでしょうか
住宅や店舗を作る際に、自治体に申請をして、各法律、法令に沿って問題がないかどうかを判断してもらう重要な申請で、多岐にわたる項目がありますが、基本的には許可をもらえる内容で設計を行いますので、ご安心ください。
隣地境界線の確定について教えてください、測量が必要ですか?
基本的には、土地の取得時に売主の負担で境界が決められますが、相続などで境界が不明な場合、計測が必要なケースもあります。
火災保険や地震保険の選択、セオリーや注意点を教えてください
建築以外に必要な費用ですので、当初から提示するようにしています。木造でも一般や、省令準耐火の種類がありますので、保険料が変わってきます。地震保険は途中で加入しにくくなるケースがあるので、当初から加入しておくことをおすすめしています。地震保険でも長期優良住宅のメリットがあります。
不動産登記の必要書類と手続きについて教えてください
基本はメーカーが段取りしていきます。都度必要書類をご案内し、手続きは司法書士さんと進めていきます。
建てる時に、相続について考えておいた方が良い事はありますか
相続税については想定しておくべきこともあります。生前での制度などもありますので、配慮される方は税理士さんへのご相談をおすすめしています。
ご近隣トラブルを防ぐために設計時に考えるべき事はありますか
詳細は住んでみないとわからないので、建設時からの印象やご挨拶などのお付き合いで、できるだけ良い関係を作ることが大事だと考えています。
災害・安全対策
レベル別防犯対策(鍵、窓、セキュリティシステム)を教えてください
玄関のドアに関しては、高い防犯性のある鍵が使われている傾向があります。ドアよりも、窓から入られるケースが多いですが、防犯と断熱を考える必要があります。左右に開く窓よりも、上下に開くドアの方が入りにくいという特徴もあるので、おすすめです。カメラも最近はWEBで監視できるものもあるので、おすすめです。
水害や地震といった災害リスクの評価を事前に知るにはどうしたらいいですか
ハザードマップや、ジャパンホームシールドで出している地盤のサポートマップというアプリもあり、活用するのもありです。
防火性のある建材を使用した方がいいですか
省令準耐火の建材も値段が大きく変わることはなくなってきていますので、積極的に活用します。
地震、落雷や停電時の対策として必要な考え方を教えてください
落雷自体を避ける予防というよりも、実際に電源が落ちた時に家電を保護するような機器を使うのがおすすめです。感震ブレーカーという機材もありますので、地震が心配な方は検討を。
災害時の避難や備蓄に対する考え方を教えてください
備蓄用の場所を作るというより、備蓄は普段の食糧庫との兼用になると思うので、少し場所を空けておくようにしましょう。地震の際の避難経路については、戸建の場合は、玄関までの2つの経路があることなども大事です。そもそも、耐震性の高い住宅にしておくのが一番大事です。
ネズミなどの害獣対策って北海道でも必要ですか
床下換気口などから侵入してしまうケースが多いので、基礎断熱で換気口を避けることなど対策はありますが、隙間に齧り付いて侵入されることもあります。必ず避けられるという方法はないですが、できる限り寄ってこないように、住宅の周りに棲みかとなるようなものをなくしておきましょう。
ライフスタイルや将来性
バリアフリー設計はどれ位やっておいた方が良いですか
今は標準で基本的にはバリアフリー設計となっているので、あまり考えなくて大丈夫かと思います。
ペットがいる場合の注意点、工夫することはありますか
ペットの種類にもよりますが、小型犬であれば滑りにくい床にすることや、尿の染み込みを防ぐ対策が考えられます。猫については爪研ぎをするので、ペットに対応した強度の高い壁材など、対策が可能です。
家庭菜園や庭、注意点はありますか
家庭菜園だと虫がどうしても増えるので、家に虫が入るリスクは高まります。庭については、趣味でデザインも変わると思うので、可変的な前提を持つと良いと思います。
車の駐車スペースを考える際の注意点を教えてください
今乗っている車プラス一回りの大きさを考えておくと良いです。まず初めに敷地内の駐車スペースを考えて、間取りも考えていきます。
資産価値の維持と将来的な売却のし易さを教えてください
大事なご質問ですので、ぜひこちらをご覧ください。
【価格と未来の価値】
将来のリフォームの可能性を予想する方法、要素はありますか
建てる段階でリフォームのことを気にされる方は少ないですが、例えば、将来の同居や、仏壇が置かれるケースなど、その後に予想できるものについてはできる限り確認するようにしています。
将来的に賃貸住宅として利用できる可能性はありますか
北見や地方だと一戸建てで貸し出すケースは今は少ないですが、ライフスタイルに合わせた賃貸や売却の選択肢は今後増えていくと思います。自分たちが便利だと感じる立地など、客観的な視点を持つと、選択肢が広がると思います。
子供の独立後の子供部屋、利用方法や良い設計方法はありますか
利用方法は家族によって様々ですが、趣味の部屋にする場合や収納部屋にする場合もあるので、壁紙の変更や2間を1間にする設計など、汎用性を高める手法もあります。
定年後の収入と維持費のバランスはどう考えるべきですか
メンテナンス費用やランニングコストはかかるので、できるだけ将来のコストが下げられるような対策をしておくのが基本です。
美観・デザインに関すること
外観のデザインを考える際の観点、注意点はありますか
見た目のデザインだけでなく、メンテナンス性やランニングコストも含めた総合的な判断が必要です。
内装の色や素材の選択する際のセオリーを教えてください
広さ、色味、素材感など、大まかな好みは将来的にもあまり変わらないことが多いので、基本の好みを理解しておくことが重要です。
「いいな」と思う家のデザインを集めていただき、それを踏まえて素材のメリット・デメリットなどを判断してもらうと、決めやすくなります。
住む家族それぞれの好みや意見も関係するので、決め方自体をあらかじめ決めておくのも大切です。視点による見え方の違いを意識し、空間全体の中で個々の意見を反映させる方法もあります。
外構を考える時の基本を教えてください
家を優先して外構を考えると、いつまでも手をかけられないことが多いので、ある程度のウェイトを最初に決めておくと良いです。
照明を考える時の基本を教えてください
その空間でどう過ごしたいかを、場所ごとに考えると、素敵な空間やライティングを作り出すことができます。安らぐ空間なのか、アクティブに動く場所なのかなど、目的を考えていくと、空間がまとまってきます。
その他の考慮事項
趣味やライフスタイルに特化した設計を導入する時の注意点はありますか
趣味や好みを反映しつつ、使い勝手や汎用性なども含めた設計をすることが大切です。本人のミクロな目線と、家族からの目線や資産価値などマクロな目線の両方を考慮して設計することが重要です。
プライバシーのための外壁や塀を設置する時の注意点はありますか
塀などはプライバシーを高める一方で、北国では除雪のしやすさも考慮して設置するようにしましょう。
自然災害後のリカバリーを意識した設計ってありますか
耐震構造を意識しておくと、万が一構造部分が毀損しても、補強や修繕がしやすくなります。災害に対しては、最初から災害に強い家にする考え方が重要だと思います。
年齢や健康状態に応じた設計の観点ってあるんでしょうか
住宅においては、ユニバーサルデザインというよりも、その家、その時の状況に応じて改修できる機能を少しずつ加えていく考え方が良いと思います。手すりの使い勝手も、持病や体の癖に応じて変わるため、その都度考えるのがベストです。
ランニングコストの見通しは立てられますか
インフレやエネルギー価格の予測は難しいですが、現時点の数字を元に予測することは可能です。
ガレージをつくる際の注意点やテクニックを教えてください
インナーガレージの場合、ガレージ内と住宅へのアクセスのしやすさが重要です。また、強い構造設計を施し、開口部を広めに取ることで使いやすくなります。単純に車の入る寸法に合わせると、狭くて使いにくくなる可能性があるので、注意が必要です。個別のガレージでは、外構を含めた出入りのしやすさが重要です。